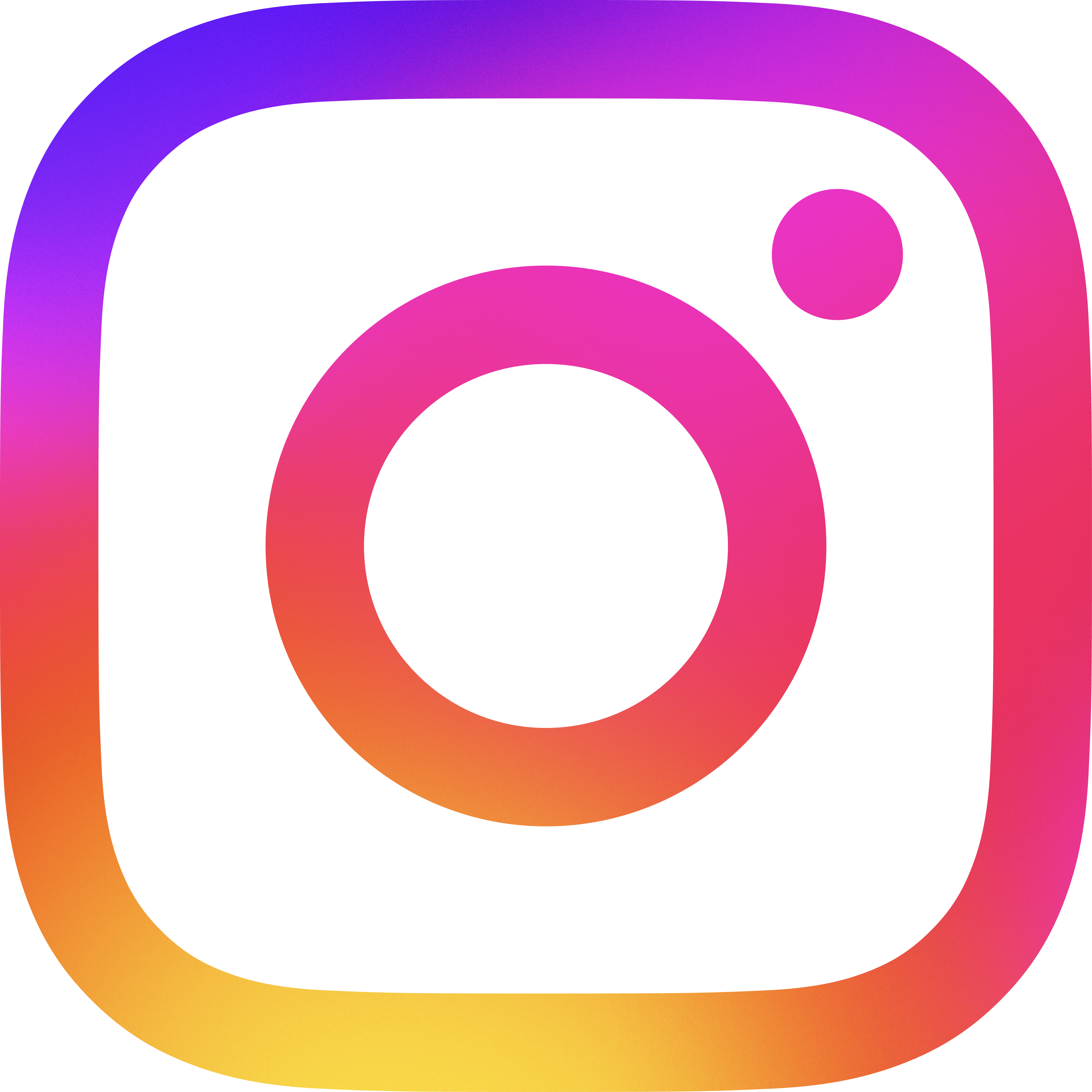2023年5月にみなさんと作った手作り味噌。季節が2つ巡って、そろそろ開封したという声も聞こえてきています。味噌の表面にカビもつかず綺麗な表面だったと教えてくださったお客様もいて、ホッとしています。
レッスンの時には味噌作りを一緒に行いましたが、開封の仕方や再び封を閉じる時の注意点を口頭でお伝えしていたので、ブログで詳しくお伝えしたいと思います。
開封してカビがついていないかチェック
リタルダンドの手作り味噌レッスンでは、味噌の上に紫蘇・サランラップ・塩の重しを乗せて新聞紙を琺瑯容器の表面に覆って保管しました。その全てを取り除いてみましょう。
紫蘇を取り除く
表面を覆っておいた紫蘇は味噌と同化したように見えるので、取りにくいですが丁寧に取り除きます。この紫蘇は食べられるので、お料理に使っても良いですし、ご飯と一緒に食べても美味しいです。
紫蘇を取り除かないとどうなる?
一度、取るのが面倒で味噌に混ぜ込んだことがあります。味噌汁に入れた時、ぷかぷかと「これは何?」と思うものが浮かんで見た目が良くないので、それ以来、面倒くさくても取り除くようにしています。「気にしない!」という方はそのままにしてください。
カビがもし生えていたら?
もしカビが生えていたら、スプーンやバターナイフなどでカビ部分を丁寧に取り除きましょう。リタルダンドの味噌レッスンで作った方のほとんどの方は(私が伺った人のみなので100%とは言えません。)カビがなかったと仰っていたので、ほとんどの場合は大丈夫じゃないかなぁと思います。
塩の重しは再利用
塩の重しは再利用します。初めて開封する時にはひしおが上がってきているので、袋がひしおまみれになっているかもしれません。流水で洗いながらして、乾いたタオルやペーパータオルの上に置いて、しっかり水分を摂りましょう。
味噌を小分けの保存容器に移す
日常で使いやすいサイズの保存容器に味噌を移しましょう。

使用するヘラは念の為、アルコールで拭き取る or 煮沸消毒して滅菌してください。私はパストリーゼを使っています。
味噌の表面はしっかりならして平にしてください。余計な空気が入らないようにしましょう。

再び封を閉じる
再び味噌樽を締めます。
次回、開けた時にもカビが発生しないように丁寧に扱いましょう。
容器を綺麗に保つ
内側についた味噌をヘラなどを使って綺麗にこそいでおきます。

水で適度に濡らしたペーパータオルを使って、余分な味噌を拭き取りましょう。

もう一度、綺麗なペーパータオルを適度に折りたたみ、アルコール(パストリーゼ)を染み込ませて、容器内側を拭き取ります。

表面にサランラップをべたっと敷き込みます(べたラップ)。空気が入り込まないように、手の甲などを使ってぎゅっぎゅっと圧迫します。その上に塩の重しを乗せて空気を抜きます。

付属のプラスチック蓋は使わずに、琺瑯蓋をかぶせるだけで大丈夫です。今回からは取り出した味噌がなくなるたびに、ちょこちょこ開封しなければならないので、新聞紙などの紙で蓋をする必要はありません。塩の重しでしっかり表面が覆われて、琺瑯蓋があれば埃が入る心配もないです。

多分、1〜2ヶ月ごとに開封して小分け容器に取り分けながら使用することになると思います。その都度、表面を清潔に保つようにしてください。

天地返しは必要?
レッスンでもお伝えしていますが、天地返しは特に必要ないと思います。あまりベタベタ触らずに、表面から使っていけば雑菌が入る心配も減ります。
リタルダンドの手作り味噌作り講座
2024年の味噌レッスンは4月か5月を予定しています。まだまだ感染症が気になる季節…寒い時期は換気しずらいので、少し暖かくなってから味噌を仕込みましょう。
味噌の仕込みはいつでも行うことができます。でも夏だけはオススメしません。
1度だけ8月に仕込んだことがあるのだけれど…圧力鍋の熱気で暑くて、暑くて、汗だくで仕込む羽目になりました。ちょっと涼しいぐらいがちょうど良いかなと思ってます。
味噌作りに合うおすすめ容器
味噌講座の時に質問されることNo.1が保存容器についてです。素材は?サイズは?どんなものが良いでしょう?
ジップロックでもタッパーでも出来るんだけど、おすすめしているのは琺瑯容器です。開口部が大きくて、寸胴のものが良いです。詳しくは手作り味噌に最適な保存容器|琺瑯を選ぶ理由と使い方をご覧ください。
味噌の変化を楽しむ
レッスンで仕込んだ味噌は4kgほどです。三人家族なら1年くらいは楽しめる量じゃないかと思います。味噌は呼吸をして発酵します。時間が経つごとに濃く熟成します。自分の手でこねて、自分の家で熟成していく自家製味噌。味の変化も楽しんで下さいね。